
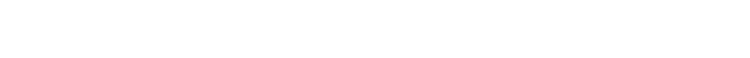
Vol.5
大谷 雅彦
短歌という短い文芸様式において、「文体」というものが存在しうるのかどうかについて、前回の拙文の末尾で、たしかに存在すると書いた。短歌における文体が、散文におけるそれのように、いかにもその作者らしい特徴が滲み出てくるようなものなのかというと、すこしようすはちがうようだ。
一首の短歌作品を読んで、その作者が誰であるかを言い当てるのは、正直むずかしい。短歌専門雑誌に発表されて多くの人の目にとまり、あるいは批評に取り上げられて広く紹介されたような歌の場合はべつとして、毎月刊行される結社雑誌に発表された歌のどれかを、作者名を伏せて示されたとき、その結社のベテラン会員であっても、正確に作者を言い当てることは至難の業であろう。
短歌の場合、一首はわずか三十一音で構成されている。この三十一音を五つの句に振り分けるのである。短歌には千数百年の歴史があるので、俳句ほどではないとしても、どうしても似たような表現になってしまう場合がある。五七調あるいは七五調の調べに乗った語句、古来より美しい、上手であると高く評価された語句は歌人の間で共有されているので、自分の作品を創作するときに、息を吐くようにしばしば出てきてしまうのである。古典和歌の時代には枕詞や序詞が修辞の一つとして用いられていたのであるが、例えば柿本人麻呂作とされる短歌「あしひきの山鳥の尾のしだり尾の長々し夜をひとりかも寝む」(「万葉集」第十一巻二八〇二番)では、「あしひきの山鳥の尾のしだり尾の」が序詞であり、次の「長々し」に掛かっているというのである。しかしこの部分は作者個人の独自の表現とはいえない。決まりきった、あまりにも有名なフレーズである。そうなると、この歌のなかで作者が独自に言葉を組み合わせて表現しているのは「夜をひとりかも寝む」の部分だけで、果たしてこの部分に作者のオリジナリティーが存在するのかと疑問に思う人もあるだろう。初めてこの序詞を用いた作者はともかく、この歌の存在を知りながら、次におなじ序詞を用いて新しい歌を作ろうとすると、かなり窮屈な思いをすることになってしまう。十七音を使ってしまう序詞はどうにも動かしようがなく、残された二句十四音で新しい作品を作らなければならないのである。しかも、序詞が「長々し」に掛かっているので、自由に使える音数はさらに少なくなっている。
序詞は音数が長すぎて新しい作品を作るうえではどうにも身動きが取れない、というので現代ではほとんど使われていない。「ひさかたの」などの枕詞も、序詞よりは短いものの、通常五音を消費し、次に掛かる言葉(「ひさかたの」の場合は「光」「雨」「天」など)も特定のものに決められているので、自由度はそれほど高くはない。本歌取り(ほんかどり)という修辞法もあるが、これはすでに有名な短歌として世に広まっている作品の一部を序詞のように自分の歌のなかに取り入れることによって、有名な作品を今一度読者に想い起こさせ、その作品にたいする作者の想いを一ひねりして表出する、という修辞法である。たんに有名な短歌を導き出しただけでは作者自身をアピールすることができず、修辞技法としては非常に難易度が高いといえる。
作者の個性を一首のなかにきちんと盛り込むために、現代の短歌作者に残された方法は何か……。
音数(文字数)の少ない形式なので、一語一語に気を遣い一文字一文字に心を砕く。それしかないように思われるのである。「烏」ではなく「鴉」を使ったり、漢語を仮名書きにしてみたり、漢字の使用を極端に減らして平仮名に変えてみたり、とできるかぎりの工夫をする。
それにしても、使用可能な文字数があまりにも少ない。通常の日本語の散文のように、「主語+修飾語+述語」の形をわざと崩して倒置法に変えてみたり、さらにその一部を省略してみたり……。通常の文法の概念からはかなり外れた言葉の使いかたになってしまったりすることもある。短歌という定型に何とか嵌めこもうとしているので、読者にしても、表現したいところはなんとなくわかる……そのような危ういぎりぎりのところで現代短歌は作られている。
さらに、一首のみでは弱い、ということで、連作(れんさく)という手法もしばしば用いられる。テーマに沿った作品を数首あるいは数十首まとめて発表することで、作者のオリジナリティーをはっきり主張したいということであろう。歌の対象となる自然現象や動植物あるいは人間など、特定の事物につよくこだわりを持って歌いつづける場合もある。一つ一つの漢字へのこだわりや仮名遣いの工夫などは、一首だけではあまり目立たないかもしれないが、数十首に及ぶ連作となると、それなりに作者像が立ち上ってくる。短歌における文体とはそのようなものであろうか。
数年間をかけて読みつづけてきた明治・大正・昭和時代の短歌作品約十五万首を先日ようやく読了したのだが、どの時代にも言葉そのものと真摯に向きあってきた歌人の姿があった。戦後の一時期、短歌のような古い文芸様式は不要であるといわれたこともあったが、そんなに簡単には消え去らなかった。日本語がよほど大きく変貌しないかぎり、短歌や俳句といった伝統詩型は漢字や仮名など豊かな文字とともにしっかりとこの国に残っていくことだろう。
(終わり)

1958年兵庫県生まれ。歌人。
立命館大学卒業。1976年「角川短歌賞」を受賞。歌集『白き路』(1995年)、『一期一会』(2009年)。
※写真:大賀一郎博士により2,000年前の地層から発見されたという「大賀蓮」と、アメリカから贈られた「王子蓮」との交配により生まれた「舞妃蓮(まいひれん)」。皇居に献上された蓮です。写真は、大谷氏よりご提供いただいたものです。