
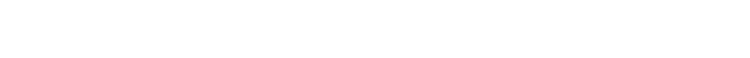
Vol.7
シュテファン・カイザー
超漢字マガジンインタビュー第4弾(VOL.7)は、ドイツご出身の日本語学者、シュテファン・カイザー先生です。
前編では、外国人から見た日本語の魅力や、日本語学習の課題、日本人が外国語を学ぶコツや、幕末から明治時代にかけて横浜の外国人居留地で使用されていた言語である「横浜ダイアレクト(ピジン日本語)」(ピジン言語=2種以上の言語が接触して発生する言語)など、外国人と日本語の関係を中心にお話を伺いました。
――先生が最初に「日本」という国をお知りになって、日本語に触れられたのはいつごろでしょうか。
高校を出てからですね。高校を出たときに親父に「世界一周してこい」と言われて、その計画の段階です。計画では、まずアメリカに渡って、メキシコに行って、次に日本、そのあとネパールやインドに行く予定だったんですが、結局は日本でスタックしてしまって(笑)、6カ月くらい滞在していましたね。
メキシコを訪れたとき、スペイン語は知りませんでしたし、マヤの遺跡を見に行きましたけれど、特にマヤ語には興味がわかなかったんです。でも、どういうわけか、日本語については、そのときすでにローマ字で書かれた簡単なテキストを購入していたんですね。その本が日本語に触れた最初ですね。
――それまで、日本語に触れられたことはなかったのですか?
多少書籍とかでは。ドイツでは、日本に関する書籍は多少あったんですが、日本語に関するものはぜんぜんなくて。100年前の(幕末の)開国時代に宣教師などが書いたものがあるくらいでした。それで、購入したのは英語のものでしたね。「Teach Yourself」という語学のシリーズがあるんですが、日本語を扱うものはそれしかなかったですね。ドイツ語で日本語を語学として扱うものはまったくなかったんですね。
――では、実際に「日本」にいらしたときの最初の印象はどのようなものでしたか。

おいしい!(笑)
――食事が気に入られたのですね。
すごく気に入りました。小さいときから親父が健康食志向だったので、精米していないような穀物を食べさせられていたせいで、米は大嫌いでした。でも、日本で食べてみたら「え?!こんなにおいしいものだったのか!」と。初日から「これはすごいな」と。
――日本には、6カ月間いらっしゃったということですが、東京を中心に滞在されていたのですか?
いや、京都が中心でしたね。困ったことに。
――「困ったこと」ですか?
ホームステイ先は女性が多くて、男性と女性の話し方の区別があるとはぜんぜん知らずに、そのまま吸収してしまいました。アクセントもです。あとで直すのにかなり苦労しました。
――たしかに京都は男女の言葉の差が強いですよね。それで、日本に滞在されてしまったということでしたが、結局、日本から先の行程は全部キャンセルされて、そのままドイツに戻られたということですか?
そうですね。当時のドイツは学校が4月から始まっていたので、3月まで日本にいて、4月からドイツの大学に入りました。
――ドイツで最初に研究されたのは、何だったのでしょうか。
やはり日本語やアジアの言語ですね。当時は中国語もやっていたんですけれど。でもドイツでの研究は1年で切り上げてしまったんです。
――では、その後ロンドン大学に行かれたのですか。
はい。ドイツの大学は程度がすごく低かったんです。
――先生がいらっしゃったのは、ロンドン大学の東洋アフリカ研究学院(SOAS)ですよね。SOASは東洋についてはやはり、ヨーロッパの中でも最高クラスでしたか?
ヨーロッパの中では最高のランクのひとつだと思います。もともとSOASができた経緯が、植民地でそのまま役に立つ人材を育てるということで、当初は東洋だけであとからアフリカが加わったんです。SOASは、オックスフォード、ケンブリッジなど、ほかの大学とは違って、文学を勉強するのではなくて、実用的な日本語を身につけられる程度の高いプログラムだったということがまずありました。それに加えて、戦争で日本と戦っていたのがイギリスやアメリカなどだったので、戦時中に日本語にものすごく力を入れていたんですね。『戦中ロンドン日本語学校』 (大庭 定男 著、中公新書、1988年)という新書があるんですが、これはイギリスのロンドン大学について書いたものなんです。
アメリカでも同じことをやっていたと思いますが、大学生のトップの5パーセントを引き抜いて、「お前たちはどうせ軍人になるだろうから将校にならないか? そのかわり日本語を覚えなければならない」と、特注のプログラムを作っていたそうです。ドナルド・キーンやサイデンステッカーもそういうところの出身なんです。ロンドン大学の教授陣もみんなそうだったんです。その中でも特に優秀な人が大学院に残って……。ところがドイツにはそういうのがぜんぜんなかったんですね。信じられないくらい日本語の研究については雲泥の差があったわけです。それでなおさら日本語研究は英語圏のレベルが高かったわけですね。国際的な研究というのが当初からあったんですね。ドイツの日本語研究は、ドイツだけで、という感じだったんですが、英語圏では国際舞台で繋がっていたし、外国からくる学生も多かったです。
――それで、SOASを選ばれて日本語の研究をしようとロンドンにお移りになったわけですね。SOASでは日本語のなかでもどのような研究をされたのでしょうか。
4年制の学部だったので、特に専門というのはないわけですけど、やはり「日本語」そのものということで、翻訳あり、作文あり、そういう実用的なことですね。最終試験のときには会話の試験もありました。
――欧米の方でも日本語をきれいなイントネーションでペラペラに話せる方もいらっしゃいますけど、書くとなるとなかなか難しいのではないですか。
書くのも難しいですし、読むのも難しいですね。よく思い出すのは、当時シニア・コモンルームという、学生も入ることができるスタッフの社交の場みたいなところがあったんです。そこに西洋人らしき人が来て、座って、静かに日本語の本を開けて読み進めるということは、年に1回あるかないかでした。そういうことがあると、噂が即座に広まって、みんなで見にいくんです。それほど珍しいものなのですよね。日本語で話せるようになるのはどうってことはないし、聞けるようにもなります。ただ、読むとなるとまず、百人に一人とか、千人に一人とか、あるいはもっと少ないかもしれません。本当に深刻だと思います。
――そんなに少ないんですか。その中で、先生は大学の4年間で読んだり書いたりもおできになったんですよね。
ええ、一応。
――それはやっていくうちにだんだんと? 最初は辞書を引きながらでしょうか?

そうですね。日本からドイツに帰るとき、山本有三の『不惜身命』という旧漢字と旧かなで書いてある歴史小説をたまたまもらっちゃったんですね。ベルリンの大学にいたときは、授業のレベルが低くてつまらなかったんで、家にこもってそれを読もうと。最初は辞書を引き引き……1日で1行の半分くらいですかね。それがだんだん増えて、少しずつ長くなって、全部読んでしまいました。半年くらいですかね。
――今だと若い人でもてこずるような本ですが、それをドイツの大学にいる間に読みきられたんですね! 先生は、ずっと独学だったんですよね?
独学ですね。さっき教材がなかったという話をしましたけれども、アメリカに行ったときに、すぐに本屋にいって探したんです。そうすると、ライシャワーとエリセーエフというハーバード大学の人たちが作った大学生向けの日本語の教科書(※)があって、アメリカをまわりながら漢字のマスを埋めたりしていましたね。
※ Serge Elisseeff and Edwin O. Reischauer, Elementary Japanese for University Students, Harvard-Yenching Institute, 1941.
――そこまでおやりになったというのは、日本語のなにかが……。
「なにか」があったんでしょうね。ただ、言葉に才能があるというか、あまり苦にならないという意識があって、大学に入ったら言葉のことはやろうと思っていたので。(ドイツ)近辺の言葉は、似たような言語なのでやっていてもつまらなくて。はっきり言って、あまり面白くないんですね。日本語は接してみたら「これはまるっきり違うものだ」と。そのときは、はっきりと意識してはいなかったんだけど「これかな」という。
――日本語はひらがなから覚えられたのですか? ローマ字表記と対比させながらでしょうか。それとも、まず話すことを先にしたのでしょうか。
アメリカの教科書を使って、アメリカを3カ月くらい回っている間に覚えたんですけど、その中にはもう漢字も入っていましたね。それを少しずつ、日本にいながらもやっていたんです。学校にはぜんぜん行っていないですね。あとは周りのことばを聴きながら、ですね。今でも覚えているんですけれど、日本に来て3カ月くらいたったころですか、タクシーに日本人と3人で乗っていて、最初は日本人同士で会話をしていたんですが、知らないうちにいつの間にか会話に加わっていたんですね。本人もびっくりというか。
――ふつうに一緒に話されていたと。では、文字を覚えるときは、ひたすら書いて覚えられたのでしょうか?
私の場合は、最初に『不惜身命』を取りつかれたかのようにやっていたので。やり方は自分で考えたんですけど、まずは辞書を引き引き、単語を引いて、文法を考えて、単語リストを作るんですね。次に、夜、寝る前に記憶にいったんいれるんですね。ベッドに入って電気を消して、全部思い出そうとする。思い出せないものは電気をつけて確認。また電気を消して……と一所懸命に覚えて。そして、朝、目が覚めるときに、まず思い出そうとする。思い出せないものはまたチェック。それから本に戻って、まずはコンテクスト(文脈)の中で前の日にやったものを意味を考えながら読み返して、その後次の文にいくという方法です。だからやはりコンテクストですね。ただ覚えるだけじゃなくて、コンテクストの中で記憶に定着するだろうと思ってやっていたんですね。
――そこまでされていたのですね! そうやってコツコツとボキャブラリーを増やしながら、読み進めていかれたんですね。
大学1年生というのは、われわれは開放感があるんです。(大学)入試はないし。ただ、学校から開放されたという感じがはあるんですね。自分の嫌いな科目とバイバイできて、大学で選んだ自分の好きなことに一所懸命打ち込むことができるんですよね。受験勉強で疲れている、という状況にはないんですね(笑)。