
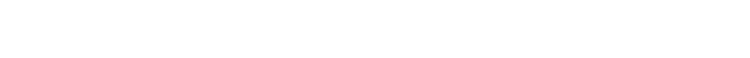
Vol.15
日暮雅通
――今回のエッセイや『シャーロッキアン翻訳家 最初の挨拶』を読ませていただいて、ホームズの訳でも、カタカナの使用範囲などで日本語の古い訳と新しい訳が少しずつ違ってきているということがわかりましたが、海外での翻訳でもいろいろと問題があるということも初めて知りました。Irene Adlerの名前は、自分の中に最初にインプットされたのは「アイリーン」だったんですが、エッセイに書かれていた全部の翻訳パターンを見たことがあって、なんで名前が違うんだろうと思ったことがありました。
典型的には、イギリス英語とアメリカ英語の違いですけどね。同じアルファベットを使う国でそれぞれ発音が違うという。人名にはどうしてもそういうところがあって、ドイツ語ならピーターがペーターになるとか。ただ、日本語はアルファベットじゃないから、カタカナにしたときに、非常に面倒くさいことになるわけですね。要するに彼らは頭の中では自分の国の発音で読んでいるわけですよ。Ireneをイギリス人は頭の中で「アイリーニ」と読んでいるし、Peterと書いてあってもドイツ人は頭の中で「ペーター」と読んでいる。それで問題はないんだけれど、日本人の場合は、「ペーター」なのか「ピーター」なのかで字の見た目も変わってしまう。そういう問題はしょっちゅう起こりますね。
――発音によって書かれている背景の国が変わってしまうこともあるんですね。英語からフランス語、ドイツ語、ロシア語……各国のそれぞれの翻訳家の方にもいろいろと苦労があるんですね。日本語よりは簡単に翻訳されているのだと思っていたのですが。

英語から何語に変えるかによって、手間や制限は変わってくると思います。相手の言語と同じ表現がこちらの言語側で存在しなければ、変えなくてはならない。あるいは作らなければいけない。そういう問題はけっこう大きいですよね。これはさっき言ったように、言語として有る無し、カルチャーとして有る無し、時代として有る無し、その3つの要素が絡んできますね。イギリスにはあるけれどロシアにはない物をどうやって表現するか、どうやって読者にわからせるか。それから、イギリスの百数十年前には当たり前にあったが今はない物事について、どう表現するのか。そういった、時代や言語に関することですね。言語でいうと、ある言語では存在するけれども別の言語では存在しない表現というのがありますね。ヨーロッパの言語同士だったらだいたい大丈夫なんだろうけれど、スワヒリ語で存在しなかったらどうするかとか(笑)。ホームズ関係だけでも90言語くらいの訳があると言われていますが、90言語のなかでどうやって訳しているのかはわからないです。
――ノンフィクションなどで、日本人のことが英語で綴られている場合に、漢字に戻さなくちゃいけないときも困りますね。
海外の人が書いた作品で日本人が登場すると、僕らとしてはかなり困ります。漢字をあてなければいけないから。まあ、著者が考えているのと違う漢字をあてても、日本の読者にはそんなに問題はないわけだけれど、でもどれが正しいのかと悩んでしまうわけですよ。アルファベット表現は同じでも漢字にしたら何とおりもあるので、どれだろうと言っても、原著者はわからないわけだしね。
――Dr. Watsonも、昔は「ワトソン」と書かれることが多かったと思いますが、今はだいたい「ワトスン」ですよね。
「~son」と書かれる名前ですね。たとえばスティーブンソンなのか、スティーブンスンなのか。はっきりはわかりませんが、20年くらい前まではかなりの頻度で「~ソン」でしたね。今でも「~ソン」という書き方はたくさん残ってるし使ってるし。だから絶対に「~スン」にしなくちゃいけないということはないんですが、訳者によって、あるいは出版社によって、原語にできるだけ近づけたカタカナ表記にしたいという場合は「~スン」にすることが多いです。ただ、一冊の本のなかですべての単語に関して原語に近い発音のカタカナ語にできるかというと、これはまた難しい問題です。新聞や雑誌で定着している地名や単語に対して、原語に近いからといって全然違うカタカナ表記にしてしまったら、読者は戸惑ってしまうでしょう。
実際問題として、子供向けの本の場合、僕は「ワトソン」にしています。これも時代とともに変わってくると思いますが、子どもの本ではたとえば「ヴ」は使わない傾向にあります。昔の日本人や昔の子どもが「ヴ」になじみが少なかったからだという理由によると思うんですが、今の子どもたちはけっこう発音もわかっているし、英語教育も始まっている。じゃあ小学生の英語教育がどんどん普通にやっているときに「V」の表記を「ブ」と書いたらまずいんじゃないかという議論も、そろそろ出てくるかもしれませんね。たぶん今は過渡期にあると思いますよ。
――子供向けの本の翻訳のほうが寿命が短いかもしれませんね。
今は英語教育の現場も変わってきましたが、かつてはカルチャーとして映像や音楽で海外のものがどんどん入ってきて、それになじむことによって変わってきた。昔だったらクリネックスとかティッシュとかいう単語はよくわからなかったけれど、今は普通に使っているわけです。それがさらに、教育現場が変わってきていることによって、翻訳者側も対応しなくてはならなくなっている。その問題はすごく大きいです。
――(エッセイの)最後に書いていただいたのは小説や映画のタイトルに関係する話題でしたが、邦題にカタカナが乱立しているというのはまさにそのとおりですよね。
それこそ、英語教育が変わってみんなが日常的に英語を見ただけでイメージがパッと浮かぶようになったら、カタカナそのままのタイトルのほうがいいのかもしれませんがね。『カジュアル・ベイカンシー』などと。今はまだ無理だと思いますね。言葉の変遷で変わっていくとは思いますが、一方で、若い人がいまだに昔と同じ単語を使って全然気にしていない場合もあるわけですよね。「ミンチ」はいつまでたっても「メンチ」だと。それに疑問を挟む若い人はあまりいないわけですよ。そういうふうに生き残ってしまうものもあるかもしれないですね。

カタカナ語全般の問題で言うなら、たとえば技術系のもので「スマートフォン」なのか「スマートホン」なのか。電話は「phone」だから「フォン」を使うようになってきているけれど、今でも混ざっていますよね。
――「スマートフォン」だけど略すと「スマホ」なんですよね。矛盾してますけど(笑)。それも同じ文章の中で混ざって出てくるんですよね。
若い人は全然気にしてないですね。「スマフォ」っていうと逆に気持ち悪かったり。言いにくいし。短縮するときは違っていてもいいのかもしれない。
――翻訳したときに、わかっていても悩みそうですよね。
カタカナ語の統一問題を考えるときは、その辺のことまで考えないといけないから、漢字よりも統一は難しいかもしれないです。
――業界によっても使い方の定例も違うので、統一したくても「違う」といわれてしまうんですよね。日本語はある意味柔軟なので、難しいですよね。
諸刃の剣かな。日本語の柔軟さに助けられることもあります。外国語を自分のものとして受け入れる度合いというのが、日本はかなり大きいでしょう。カタカナ語としてどんどん外国語をそのまま使って、自分たちの言葉にしている。フレキシビリティは一番あるんじゃないかな。むしろ、アルファベットを使っている国同士では、たとえば英語圏とフランス語圏とかね、フランスの人たちはできるだけ英語そのものの言葉は入れないようにしようと、フランス語の言葉を大事にする姿勢でいるわけですよね。だから「computerじゃないぞ」と(フランス語ではordinateur)。だけど日本人は「コンピュータ」でどんどん使ってしまう。そのほうが楽だし。「電子計算機」ではないんですね。そのへんの国の違いやカルチャーの違いというのがあって、日本のフレキシビリティは僕はある意味良いことなんじゃないかなと、楽天的に思っています。あんまり混乱するようなことは困りますけどね。同じ言葉でも使う人が違うと違う意味になってしまったら、困る。
――言葉がコンセンサスをとれるか、すべての読者がひとつの理解になるかを見極めないといけないんですよね。
そのへん、人間はフレキシブルだから、「フォン」でも「ホン」でも同じものだということがすぐわかるというのは便利ですね。自分は「テレフォン」しか認めないという人は、誰かが「テレホン」というと抵抗感を感じるわけだけれど、ちゃんと共通認識があるから大丈夫なんですね。でもカタカナ語が問題になるIT業界などは、時代とともにどんどん新しい単語が出てくる。それに対して、かつて混乱したからと言って新しい技術が出てきたときに必ずひとつの語で統一しなければいけないか。統一しようとしたら大変なことになるし、新しい技術は常にバージョンが違ったり、ビデオテープのベータとVHSのときのように、常に二つ三つの規格が出てきて用語が違ったりする、これを阻止するのはかなり無理だと思うんですよね。そこで便利なのが、日本人のフレキシビリティなんじゃないかと。僕ら翻訳家というのはそれに対してある程度フィルターにかけるというかね、ひとつの方向に持っていくという役割を担っているんだと思います。