
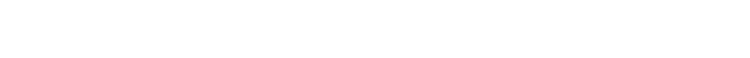
Vol.15
日暮雅通
今回のインタビューは、前回(Vol.14)に引き続き日暮雅通氏です。
後編は、前編でお話のあった「翻訳の寿命」を踏まえて時代の変化と現代語訳についてと、言葉や作品世界の文化・時代の橋渡しをする翻訳家の苦労と苦悩をお伺いしました。
――近年、一度訳されたものを新訳にするというブームがありますが、古典ほど正確な翻訳を求める声があるように思います。読者層もわかれてきて、読者が求めるものが多いと思うんですね。正確な訳が読みたいという人と、読みやすくて理解しやすいものが読みたいんだという人と。読者の要求が多様化していることについてはいかがでしょうか。
現代の作品の場合でも、正確な訳がほしいという要求と読みやすいものがほしいという要求は混ざっていますね。理想的には正確で読みやすい訳がいいわけですが、もとが非常に難しくて、そのまま訳したらわけのわからない日本語になってしまうような作品だったら、それは読みやすくしなくてはならないし、でも読みやすくする段階でもとの内容や雰囲気が破壊されてしまってはいけない。これは翻訳の一番難しいポイントで、翻訳家にとってのジレンマでもあります。
今回の僕のホームズ全集の場合は、若い読者向けという版元側の要求がありましたから、ある程度平易な文章にして、改行も多くしています。これに関して、古い時代からの読者のなかには抵抗感を持つ人もいるようですね。でもホームズものの翻訳は何種類もあり、古い訳もまだ残っているので、古い訳で楽しむこともできるし、今の20代や10代の読者のように、読みやすいほうをとることもできます。一方、読みやすいほうがよくて新しい訳で読んでいる人も、昔の訳があればそれで雰囲気を感じることもできる。そういう意味では、複数の訳が手に入る作品に関しては、読者にとってそんなに不利益はないですね。

100年前の古典の場合、本来ならば100年前の人が読んだ雰囲気は壊したくないわけですが、でもそのままの雰囲気を出そうとして旧仮名遣いになったり、古い言い回しになったりしたら、読みにくいという問題があります。そこで、さまざまな現代語訳が出てくる。たとえば源氏物語にしても、ご存知のようにいろいろな現代語訳があってそれを楽しめるわけです。シェイクスピアもたくさんの人が訳していて、場合によっては昔の人が怒るような翻訳もあるわけだけれども、それはいろんなバージョンがあるから楽しめるということですね。
――ホームズというのはいろいろな訳があっていろいろな形で出ているので、読者がそれにあわせていろいろなものを味わえるので、ある意味恵まれたシリーズなのかもしれませんね。
シェイクスピア、ホームズ、星の王子さま、それに日本の古典も、新訳というだけじゃなくて、複数のバージョンが結果的に作られていくというのは、すごくいいことですね。僕も今、ホームズもの以外の、60年くらい前に訳された古典ミステリーの新訳をしていますけれど、ミステリーはこの10年くらいの間で、古い時代のミステリーが訳し直されているし、これまで訳されなかったものも掘り起こされて出てきています。SFもそういう部分があって、エンターテインメント小説にとってはいい時代になったと思います。
――SFだと60年代くらいの作品が訳し直されていますね。
SFの場合、70年代から80年代にかけて一部で出た読みにくい訳のものも、訳し直されていますね。一方、ミステリーを含めて、戦後すぐくらいは、翻案に近い訳をしていた時代がありました。そういうものを今になって訳し直したり、新訳で出している。それが「正しい翻訳にしてほしい」ということにも繋がるんですけれどね。ホームズものも、そもそも明治大正時代は、大人向けでも日本人になじむように、舞台を日本にしたり、登場人物を日本人にしたりとか、よくやっていました。それは現在では通じないけれども、そういう時代があったことも確かです。
――舞台を日本に持ってきてしまったというのがすごいですよね。
アクロバットですよ。
――当時は許されたんでしょうけど。
読者は気にしなかったんでしょうね。むしろ読者はそれを歓迎したし、講談のように、もとの話はひとつだけどいろいろな人が語るうちに変わっていくとか、それに似た感じで、別にもとの舞台がロンドンだろうと、日本を舞台にして語ってくれればそれはそれでいい、そういう時代だったと思います。
――身近な世界に置き換えて、ストーリー展開を楽しんでいたんですね。
――前訳がある場合の利点と欠点というのは。
両方ありますね。前に訳した人がいる場合は、内容がすぐわかるし参考になります。自分もすでに日本語で読んでいるから頭の中にある。そういう意味では訳しやすいといったらなんですが、まったくの初めてで原書しかなくて、ゼロからスタートする作品よりは、参考になるデータがあるわけです。一方、既訳を見てしまうとそれに引きずられたり、逆に、わざと変えようとして変な訳になったり、そういうバイアスがかかってしまうという問題が非常に大きいですね。すでに古い訳があってそれを自分が新しく訳す場合は、昔の訳は読みませんという人もいます。もちろん自分が好きな作品だったら当然過去に読んでいるわけだけれど、新たに読み直すことはしないと。読み直してすぐに自分の訳に取り掛かってしまうと、どうしても影響をうけてしまう。そういう意味では、ホームズものは非常に難しいですね。影響を受ける訳が何種類もあるわけですから(笑)。
――ましてや、日暮さんはホームズの翻訳本を読み尽くされていますよね。
だからあまりに気にしてね、過去のどの翻訳家も訳していないような文章にしようと思ってしまうと、書けなくなっちゃいます。無理ですよ。どうやっても、同じ原文を訳したらどこかが誰かに似たりするわけです。5人いたら5人のなかの1人くらいは自分と同じ訳になる。普通に考えたらそうなるんです。非常に難しい表現とか特殊な表現の場合は、5人いたら5種類が全然違うものになるけれども、あいさつとか簡単な文章とかを含めて、変えたらむしろ下手くそな訳になってしまうものもあるわけです。だからもとの古い訳が非常にうまくて現在も使えて、自分もその訳文がいいんじゃないかという場合は、そんなに意地を張って変える必要もないんだなと。これは最近やっとわかってきました。最初はずいぶん反発というか、気にしてね、あまりに気にするもので先に進めなくなるということもありました。
もうひとつ、無理に前の訳の間違いを見つけようとか、前の訳よりもいい表現を見つけようとか、そういうことにこだわってしまうと駄目ですね。自然にやっているうちに間違いを見つけてしまうのは、しょうがないですが。その反面、自分の訳だって、今度は新訳だから絶対に間違いがないかというと、そんなことはないですね。時代が変わったり人が変われば、間違いが発見されることは常にあります。より良い訳文とか表現というのは、どんどん発見されていくものだから、自分の訳が絶対に良いということはありえません。

――当社でも2006年に『新・思考のための道具』を翻訳していただいたわけですが、前の版(1987年の『思考のための道具』)のときと時代の変化もあって、新版(原書改訂版)では新しい訳をお願いしました。
原書(1985年)も新版(2000年)とのギャップが15年くらいあるんですよね。
――はい。原書の新版は、後書きが新規に追加されて出し直されました。
その15年で、読者のリテラシーも変わっていますね。
――ノンフィクションなので、原書も初版と新版では訴えるものも違ってきています。初版は少し時代の先をいく話でしたが、新版のころは時代を振り返る感じになっています。
こういうノンフィクションというのは、出版された当時はあまりに新しいことを言っていて、わけがわからないとかなじみがない場合があるんですが、10年経って新訳にしてみたら、言葉そのものが浸透していて、訳しやすいというケースもあります(笑)。このジャンルは特にそうですね。僕らも助かるんですよ。斬新なアイディアとか先取りしたテクノロジー関係の考え方、昔だったら「ミーム」とか、そういうものの本というのは、出てきた当時はそれをどうやって訳すのか、すごく迷ったこともありますけど、今だったらかなりわかりますよね。
――作品の中の用語が世間にもなじんでくるんですね。
訳し直すときも、新聞や雑誌でどこまでなじまれているかに気をつけます。新聞がいちいち注をつけているようだったら要注意かなっていう感じで。
――やはりベースは新聞になりますか。
今だったらインターネットを考慮しなければならないんでしょうが、やっぱり活字の筆頭は新聞という前提ですね。もともと、単語の漢字を開くか開かないかということに関しても、新聞各社の用語の手引きをよく使っていましたからね。新聞をどこまでそういう道具として使えるかは、しだいにわからなくなってきていますが、ネットにしても、ネットのどこでなじまれているから使っていいかとか、そういう共通のものはないですからね。
――たしかにインターネットでどのくらい使われているのか検索してみることはありますが……。
たとえばコンピュータ用語でも、コンピュータ業界とか専門書を書いている人たち、あるいは研究者の側から見ると、新聞とは使い方が違ったりしますね。新聞も絶対ではないわけですが、どこに合わせるかという工夫はしなきゃいけない。カタカナ語などは特にそうですが、新聞と業界との違い、それから同じカタカナ語でも学術用語と軍事用語での違いとかも気にします。
――一般の人と少しでもその分野にかかわりのある人との間に、そのあたりの温度差がありますね。
「コンピューター」なのか「コンピュータ」なのかというだけでも、たしかに違いますね。これは翻訳だけじゃなくて、日本語全体として気にするべき問題ではあります。とはいえ、どの漢字を使うか使わないかでさえ、国が決める決めないであれだけもめているんだから、カタカナ語の音引きはさらにもめると思いますよ。
――そのほかの一般的な普通の用語だと、海外のものを日本語にするという段階では、翻訳家は最前線に立たされている感じがあると思うのですが。
たしかにそうですね。翻訳という面では、カタカナ語に関しては最前線。翻訳ではない小説などを全部ひっくるめると、漢字に関しての問題がありますが、僕らの問題というのは、一般の物書きにとって問題になっていることを含めて、さらにプラスアルファでカタカナ語の問題が出てきて、普通の物書きよりは面倒くさいことをやっているなぁという気がしますね。