
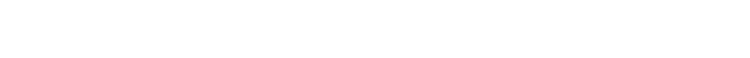
Vol.16
沖森卓也
――先生のご研究のお話を伺っていきたいのですが、日本語の歴史を研究していく意義はどのあたりにあるのでしょうか。
単に古いものが好きということでもいいと思うんですが、歴史研究の大きな意義というのは、現代を知るために、その由来というか来歴を研究するということだと思うんですよね。たとえば、なんで日本史を研究するのかというと、現代の日本の姿が作られるまでには、どういう経過があって、こういう事件があったり、こういった考えがあったりしたということを知らないと、単に今の日本だけを表面的に見ているだけでは、現代日本の社会構造や精神構造というのはなかなか把握できない。それと同じで、日本語もやはり今の日本語だけを見ているだけだと、なぜこうなっているのかというのは見えにくいところがあります。ですから、現代を知るという意味でも歴史研究というのは欠かせないものだと思うんですよね。ただ単に、古いことを明らかにしようとするというのではなくて、それを明らかにすることによって、それが現代とどのように繋がっているのかということを知ること、それがいちばん重要なことなんだろうと思います。
――現代を理解すること、ここまでの変遷を知るための過程として歴史研究が必要ということですね。歴史にもいろんなジャンルがありますが、そのなかで、日本語や漢字、文字に関する研究を選ばれたということですね。
そうですね。古代の、日本では「上代」と呼び習わしている、奈良時代以前の漢字が使われだしたころのことを研究するのが私の中心的な課題です。ですが、それだけではなくて、現代までの流れの中でその時代のそれぞれの言語事象を適切に位置づけていくことが重要だと思うんです。たとえば、「風土記」なども、現代の視点から読むのは間違いだと思うんですよ。古代人の当時の漢字の使い方や当時の考え方にしたがって、その本を読み解いていく必要がある。そういう意味で言うと、当時の漢字の使い方によって風土記を読まなきゃいけないと。それは風土記だけじゃなくて古事記だって万葉集だって同じことだけど、古代文献は当時のものとしてどのような漢字の使い方があって、それをどのように使って日本語が書かれているか、っていうことを考えていかなきゃいけないと思うんです。
現代人が古典を読み解くときに、仮名で書いてあればそのまま日本語として読めるんですけど、漢字で書いてあると必ずしもそのままでは読めないですよね。一度漢字を仮名に直す、別の言い方で言うと漢文訓読をしないと日本語として解釈できないので、それを当時の言葉に戻して、現代でも研究していくということが重要だろうと。書いてあるから、なんでも我流で読めば、意味が通じればいいというのではなくて、当時書いた人がどういうつもりで何と書いたのかということを、もう一度読み解いていくことが重要だと思うんです。
――確かに、万葉集などは研究されている方によって読み下し方も違ったりしますよね。

万葉集は、同じ本文でも読み方が違うことが多くありますね。漢字だけで書いてあったら、意味はなんとなくわかるんですよ。漢字には揺れがないとしても、漢字から浮き出る日本語が違うと読者はとまどいますよね。当時として妥当なというか、実際はこうだったという、事実をあぶりだすような研究がやはり重要です。それはもちろん古い物事の研究だけにとどまっているように見えるけれど、事実としての重みは現代人から見てもよりどころとして評価していただけると思います。
――先ほどお話に出た「正倉院文書」や上代の「風土記」、「万葉集」など、日本に残っている非常に古い文字資料について、時代を経てたくさんの方が研究を重ねてこられてきていますよね。先生は「風土記」を研究して再評価をする作業をされていらっしゃいますが、そういった研究を改めてされているというのも、当時の言葉が今にどう繋がっているかを調べるために非常に重要ということでしょうか。
別の言い方をすると、きちんとしたテキストを作りたいという思いがあるんですよ。いろんな風土記が研究者によって漢字ひらがな交じり文にされていますけれど、でもそれって本当に当時の読み方だったのかなあと疑問に思われる点も少なくないんです。ただ、それもそうなんですが、あまり多くの人が気づいていないようなことで、実はもっと根本的な問題が横たわっているんですよ。古典というのは写本があって、写本のいくつかの中からいちばん良いものを「底本(そこぼん)」として取り出して、その底本といろんな写本を対比させて本文(ほんもん)を校定するわけです。校定というのは実は作り上げることなんですよね。自分なりに作り上げる作業がいわゆる校定なんです。人によって原本に忠実にする人もいれば、「私はこう思うから、これはこうだ」と本文を勝手に作り変えてしまう人もいないわけではありません。いろんな本が出されていても、どれも部分的に違ったりするんですよ。読み方はもちろん違いますけれど、原文の作り方も違っているんですよ。古典の本文全般に、同じ状況が想定できるのですが、風土記は古事記なんかよりもはるかに本文の異同が多いんです。だから、原文を校定するという作業の中で、かなり恣意的に変えられてきたことも事実です。それで、やってみると非常に面白かったんです。
風土記は今3人で共同研究しているんですが、最初は『歌経標式』という本からはじめました。語学と文学と歴史という違う分野の人間が集まって読み解いていくと、三本の矢じゃないですけれど、折れにくい。文学の人は文学的なことに興味の中心があり、語学の人は語学的な側面から見る傾向があり、歴史の人も歴史学の立場に重点を置きますよね。だから、専門が深化すればするほど専門外のことに疎くなり、自分の専門領域から見るとこう見えるという見方しかできなくなってしまいます。でも、これらを束ねたらどこからみてもまあまあ批判に耐えられるものができるだろうと。たぶんこれからも続けていくだろうし、これは実に重要なことだと思っているんですよね。大家の先生であれば、自分の本にしたい、「○○万葉」とか「○○源氏」とか、自分ひとりでやってみたい、と願うのも無理もないことだと思うんですよ。それはそれでその人の見方だから良いと思うんですが、私たちはもっと客観的に、事実としてどこから見てもゆがみのないものをぜひとも作っていきたいと思っているので、これからも3人の協業でやっていくでしょう。

『古代氏文集―住吉大社神代記・古語拾遺・新撰
亀相記・高橋氏文・秦氏本系帳』山川出版社
今までやってきた中で『歌経標式』のほかには『上宮聖徳法王帝説』とか、藤原氏の『藤氏家伝』とか、『古代氏文集(こだいうじぶみしゅう)』とかあります。「氏文集」というのは、それぞれの氏、苗字ですよね、高橋さんなら高橋さんの家の由来というものが書いてあるものです。こういったものを集めて本文を校訂しました。一つ一つはそんなに長くないものだから、一冊にはできないので、いくつかを集めて一冊の本にしています。漢文を全部読み下して、総ルビにして振り仮名をつけてあります。本当にそう読んだかどうかは保証のかぎりではありませんが、できるだけ誠実に、客観的な読み方を心がけたつもりです。
――高橋さんや秦さんの個人的なおうちの系譜が21世紀まで残っているということですね。
自分の祖先のことを大切にしているということですね。書いてあることは、先祖が神様と結びついているということをアピールしたいためなんです。これほど家柄が良いのだとか、もう少し特別に扱ってほしいとか、そんなことを訴えているんです。
――秦氏は渡来系で古くから文書を扱う氏族ですよね。だから文献とかも代々大切にされていたことの証なんでしょうね。神社などはその謂れを受け継いできているんでしょうが。
こういうものって古いものは案外少ないんですよ。もちろんどの神社にもこういった由来のものはあるんだけれども、平安時代のはじめのころまでのものというのはそれほど多くないんです。だから「上代のものは全部やりたいね」とは言っているんだけど。
いつ集まって何を研究したかという研究会の活動の記録も残してあります。06年に万葉をやっているんですが、08年に『新撰亀相記』と『住吉大社神代記』をやっていました。
――ほかの先生方もそれぞれご自身のご研究もあってお忙しいなか、時間を作って集まっていらっしゃるんですね。
多いときには一月に2回くらい集まるときもあります。それでやってみると非常に面白かったんですよ。自分のメインでない分野について、隣接するジャンルの専門家の意見を聞くというのは実に面白いものです。年齢もほとんど同じというか同期ですから、お互いに言いたいことも言える。共同研究といっても、先生と弟子とが一緒にというのでは、なかなか共同研究にはなりません。先生の言うことを弟子が下作業するだけの話になりがちですよね。そうじゃないのがいいのですが、それがなかなか難しくて、僕はたまたまうまく仲間にめぐり会えましたけれど、みんながみなそうできるわけではないですよね。
――先生のご著書『日本語の誕生』には、文献だけでなく木簡や鏡に彫られている文字も紹介されていますね。
この本は、漢字が日本に伝わってきたころに、日本語とどんな出会いがあったのかということを書いた本ですね。
――いろんなところに文字が書かれていたんですね。
(書かれているものと)同時に、漢字は漢字なんだけど、これは日本語のための漢字なんだという視点がいちばん重要だと思うんです。
――出土した鉄剣に「ワカタケル」という表記が見つかったりしているんですね。
それも当時の人が、当時と言っても渡来系の人たちが書いたものではあるんですけど、その人たちが日本語をどんなふうに意識して書いていたのか、ということを考えると、やはり重要な位置を占めますよね。重要な資料です。漢字がまとまった形で出てくることはなかなかないものだから。
こういう古代のものって、いい資料が出てくると、突然大きく説が変わるってこともありうるんですよ。飛び飛びの年代にしか資料がなく、その資料がない時代ではどうだったのかよくわからないところに、良い資料が出てくると、またその解釈がいろいろと変わってくるっていうことなので。楽しみは楽しみなんだけど、どんなのが出てくるだろう、困ったのが出てこないといいな、というところなんですよね(笑)。
――意外と海外に残っていたりすることもあるんですか。
古代のものはあまりないですね。仏像や絵巻物、絵など中世以降のものはありますよね。絵巻物は海外にたくさん残っています。絵のほうが海外の人もよくわかりますからね。
私の研究は上代がメインなんですけど、日本語の歴史を真剣に考え出した、通史的なものを考え出したのは、1989年におうふうから『日本語史』という本を出したときなんですよね。それまでもなんとなく考えてはいたんですけど、はじめて具体的に自分で編者となって本を書いていくところで「日本語史」というものを、古代から現代までの通史で考えるようになりました。当時「日本語史」と名乗った本はなくて、これが最初なんです。今はもう「日本語史」と普通に言われますけれど。
――大学のテキストとして使われたんですね。
ええ。それと相前後して出したのが『資料 日本語史』で、これはもう写真だけの資料集です。そのころから日本語史を通史的に考えて、現代との関わりはどうなのかな、というそのあたりの視点を強く持つようになってきました。研究論文という形では書かないですけど、『日本語史概説』や『はじめて読む日本語の歴史』にはまとめて述べたところもあります。文法史なんかにも興味を持っているところに「現代語への過程」という視点を持つようになり、自分の中では現代語が少し見えるようになってきたという実感があります。

『日本語史』 『資料 日本語史』おうふう
たとえば、否定の助動詞がありますよね。「~ない」というのが否定の助動詞で、「行かない」とか「食べない」とか。形容詞にも「ない」があって、「お金がない」の「ない」は形容詞です。これと「行かない」の「~ない」の助動詞は、現代人は同じように思っている節がありますが、本来は別物なんです。日本語の歴史で言うと、否定の助動詞というのは「~ず」なんですよね。「ず」があって、活用すると「ず」「ぬ」「ね」になるんです。現代語への過程のなかで何が起こったかというと、古代語の終止形が滅びて、連体形が終止形として用いられるようになった。つまり「ず」の代わりに「ぬ」が用いられるようになったんだけど、しだいに「ぬ」の母音が落ちて「ん」になったわけです。だから「行かん」とか「あかん」といった「ん」が本来の日本語の歴史から言うと否定の助動詞なんです。
大阪弁で「~へん」と言いますよね。「行かへん」とか「あらへん」とか。この「~へん」というのは「ありはせん」というところから変化して「ありゃせん」が「あらへん」になるんですけど。その「~ん」という否定の助動詞が、実はある時期から江戸で「~ない」に取って変わるんです。唯一残ってるのが「行きません」などの「~ません」なんです。本来東京語では「~ない」を用いるわけですから、「~ます」は「~ませない」という言い方をするのが東京風なはずなんですよ。実は「~ませない」とか「~ましない」という言い方も幕末明治期にはあったんです。「行きませない」とか、訛った形で「行きましない」とか言うんですが、それがなぜあまり使われず、「行きません」というような、上方風の「ん」のまま用いられてきています。われわれは「~ません」の「ん」がどんなものなのかを考えずに使っていますが、でも考えてみると面白くないですか。否定の助動詞は、現代語への過程のなかで興味深いものの一つですね。
当時は用言プラス「~です」という形もたくさんあるんです。「~ませんでした」は「~ませんです」の過去形ですが、現代から見ると、「ませんです」は本来おかしいですよね。でも、明治の言文一致の時代に、いろんな苦心をして日本語を作り上げてきたのだというのを見ると、言語学的には面白い時代だったなと。そんなことを書くのもけっこう好きですね。文法史にしたって音韻史にしたって語彙にしたって、面白いことはたくさんあります。文字って言うのは言語の要素からすると、そのなかの一つですよね。
――文字だけを研究すればいいということではなく、発音だったり読み、文法、語彙、すべてに関わってくるということなんですね。