
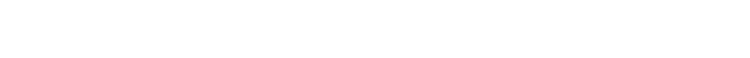
Vol.16
沖森卓也
超漢字マガジンインタビュー第9弾(Vol.16)は、日本語学、日本語史、風土記研究をはじめとする多数の著書をお持ちの国語学者、沖森卓也先生です。前編では、伊賀の沖森文庫のお話から、日本人と日本語が漢字とどう付き合ってきたのかについてお伺いしました。
――まず、先生の故郷(三重県伊賀市)の沖森書店と沖森文庫についてお伺いしたいのですが、こちらは先生のおじい様である沖森直三郎さんがつくられたんですね。
そうです。現在のウィキペディアで、私の項目には「子息」と書かれているんですが、間違いです(笑)。だから講演ではいつもこれをネタにして「タダの情報を信じてはいけない」と言っているんです。ちゃんとお金を出して買ったほうが情報は信頼できますよと。
私の祖父は大阪の鹿田松雲堂という古本屋でいわゆる丁稚奉公をして修業を積み、一本立ちして故郷の伊賀に戻ってきて通信販売の古本屋を始めました。文化的な方面にも非常に興味を持っていて、伊賀の文化を発掘したい、伊賀の文化を顕彰したいと思い、郷土の歴史研究を行うとともに、郷土に関係の深い本を趣味として集めました。その一つが松尾芭蕉を中心とした俳諧です。松尾芭蕉は伊賀の生まれですから、ふるさとの偉人を顕彰するためにも、俳諧関係の資料を集めようとしました。それと、伊賀ですから、当然伊賀流忍術ですね。忍術資料も一生懸命に収集しようとしました。この二つはほんとうに道楽というか趣味というか。そして、もちろん郷土史関係の資料も集めていました。今挙げた三つの方面はかなり重点的に集めていました。古本屋は、どこかで買って仕入れてきて、それに手数料のようなちょっと利益を上乗せして売って成り立つ商売ですから、本来は売らないといけませんよね。なのに、祖父は自分のものにしてしまうんです。そして、いわゆる「沖森文庫」といいますか、自分で集めた資料を保存していったということです。

祖父は93歳で亡くなりました。残された資料、俳諧にせよ忍術にせよ郷土史にせよ、これらは郷土である伊賀に残しておくべきですよね。できることなら寄贈もしたのですが、残された母の生活もあり、私自身の今後もありますので、「形としては沖森文庫という形で残してください」というわがままを聞いていただき、買っていただいたんです。一つ一つを売りに出してしまうと、散逸してしまって、集め直すことは大変な作業になります。ほんとうに、これは非常にありがたいことでした。俳諧関係は伊賀市、忍術関係は伊賀上野観光協会伊賀流忍術博物館に入っています。郷土史関係は図書館に寄託して、自由に見てくださいという形にしてあります。
祖父は、伊賀関係の資料を複製して故郷の偉人を顕彰しようとしたんですが、その中の一つに『伊賀善行録』の刊行がありました。しかし、この本には、付録として「古書と私」という自分の一代記を書いて載せています。実際には、自分の一代記を出版したかったから、この本を作ったと思うんですけれど、やはり書き残しておきたかったんでしょうね。
――こういったものが伊賀の図書館で閲覧できるんですね。
そうなっていると思います。それからあと、昭和の初めからそのほぼ終わりまで出していた『沖森書店古書目録』というのもあって、その時々に、どういう本がいくらで売られていたのかというのがわかるので、興味深く見てくださる方もいらっしゃいますね。
――目録も貴重な資料ですよね。取り扱っていた本の当時の歴史的な価値もわかりますし、それらの本が当時流通していたという事実もわかるわけですよね。
そのほかにも、来日中のロシア皇太子がサーベルで傷つけられたという「大津事件」、これは児島惟謙という裁判官が司法の独立を果たしたというので有名な事件ですが、その傷つけた人がロシア皇太子を警護すべき巡査で、津田三蔵という伊賀に関係の深い人なんです。その資料なんかも集めていて、大津の博物館の人は非常に興味深く解読されていました。そういったものも含めて、いろんな興味深い資料を集めていました。忍術書の『忍秘伝』とかも面白いと思いますけどね。
――忍者というと隠れ身の術や手裏剣が有名ですが、薬草や火薬の調合なども書かれているとか。
そういうのもありますけど、実際は地味ですよ(笑)。スパイなんだからあんまり目立っちゃいけない。だから、やっていることはほんとうに地味ですよ。
――そういえば、松尾芭蕉は忍者だったんじゃないかという説もありますね。
人間にはいろんな側面があるので、そういう説があってもいいんじゃないかとは思いますけれど。芭蕉にとって、その土地その土地を知ることが重要だったのでしょうね。その土地の事情を知ることが忍者の任務に繋がるかどうかはわかりませんが、俳諧の題材としていろいろな知識を得、研究を積んでいくことが俳人としての生き方に繋がっていたんだろうとは思いますね。和歌の世界には「歌枕」というのがあって、(芭蕉の旅は)和歌で詠まれている場所を訪ね歩いて、日本の古典を再確認していくという旅だったんですよ。実際、それが夢だったんでしょうね。
――(芭蕉は)昔の研究家だったんですね。
文学者ですかね。研究者兼文学者といったところですか。
――先生が日本語や漢字に興味を持たれたきっかけは何だったのでしょうか。
きっかけは特にないんですよね。生まれた家が古本屋をやっていたものだから、生まれたときから身近に漢字があったり変体仮名があったりしていたので、特にいつ興味を持ったということはありません。掛け軸に字が書いてあると、それを指して、いつも「バショウ!バショウ!」と言っていたらしいんです。「バショウ」っていうのは松尾芭蕉のことで、どうも生まれたときから日本語というか古典というか、そういうものに興味を持っていたんじゃないでしょうかね。

研究の道に入るかどうかのきっかけで言えば、家の商売がやはり古本屋だったからなんでしょうね。普通古本屋というと洋装本というか、新刊のものが古本として出回るというイメージだと思うんですが、そういうものはまったく扱っていなくて、和紙を糸で綴じた本、すなわち和本を扱う古本屋だったものですから、どうしても古典とか文学・歴史とかに興味を持つようになったんだと今では思いますね。文学でもよかったし、歴史でも語学でもよかったんですけど、なんとなくそういうのに進もうかなと思っていて。きっかけは覚えていないんですけど、自分にはどうも文学は向かないということがわかったんです。僕は近代文学、特に言文一致以前の明治前期が面白いかなと思ったんだけど、いろいろな人の論文を読んでいると、とてもこんなに上手に言葉を操って論文を書くことはできないんじゃないか、論を立てるというよりも事実に基づいて問題点を整理して物を言うほうが自分には向いているんじゃないかと思って、語学のほうに行くことに決めました。
――それは大学に入って専攻を決めるというときですか。
文学部のいわゆる国語国文学科に入ったんですが、語学の中でも専門を決めるときに、どうして漢字だったのかというと、もともと古いものが好きだったので、古いものをいろいろと読んでいくうちに、相田二郎さんの『日本の古文書』という本に出会ったんです。この研究書を読むと、いちばん最初に「正倉院文書」が出てくるんです。「正倉院文書」というのは、役所間の公文書だったり、私文書を含むいろんな文書をあつめた資料群なんですが、そういうものを語学として見ると面白いんじゃないかと思ったんです。当時そこまで研究している人はまだいなくて、卒業論文は「正倉院文書の国語学的研究」という題で書きました。そのころから、漢字とのつきあいがずっと続いているということになりますかね。
――生まれたときから古い本に囲まれて、文字があるのが当たり前の環境で育ってこられて、そのまま古い文字の世界に入っていかれたということですね。
子どものころから歴史が好きだったようで、小学校のときは伝記を読むのが好きだったんです。伝記といっても徳川家康とか織田信長とか源義経とかの類のものなんですけど、そういうのを読んでいるうちに、『読史備要』という年表だったり系図だったり花押だったりが載っている本に出会って、これが愛読書になったんです。漢字が全部読めるわけじゃないし、内容もほとんどわからないんだけれど、それを見ているのがとっても好きだったんですよね。そんなことも、一つの大きなきっかけだったかなとは思いますね。
――ご自宅にそういう本があって、自由に読める環境にあったんですね。
家での話の内容もそういう世界の話が多くて、「○○先生はこういう本が欲しいらしい」とかね。東京の神田ならお客さんがふらっと店に来ることがあるでしょうけれど、伊賀の上野までわざわざ来るわけはありません。もともと店売りなどは考えていませんでした。目録を作ってお客さんに送って、手紙なり電話なりで連絡をもらい、本を郵送してお金をもらうという通信販売を昭和の初めからやっていたんですよ。だから、お客さんの名前も、その注文もわかるわけですよね。国文学や国語学の先生が多くて、後に知ることですが、研究者として有名な先生の名前というものも、昔からよく耳にしていました。そういうこともあるから、日本の古典の世界に入ったのも自然なことだったのかなと今では思ってますけどね。